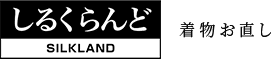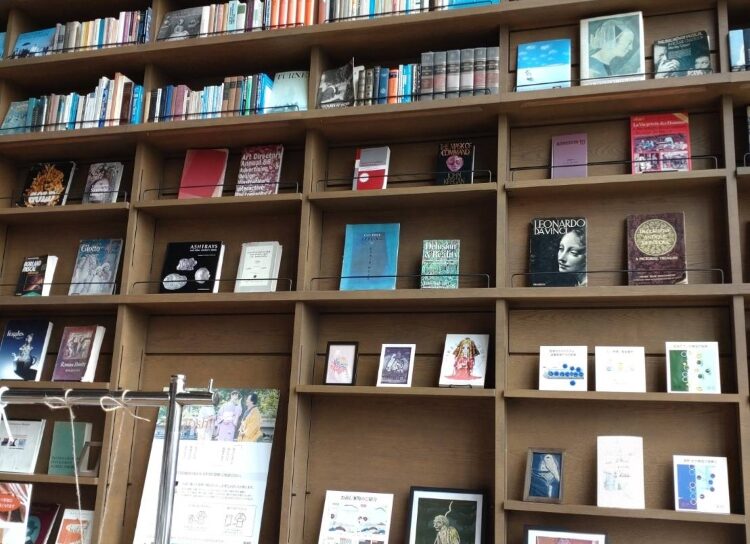しるくらんどのしみぬき日記②ー着物のしみぬきとは・昔と今ー

では、「師匠との出会い・染色補正士という職業」の二つの項目についてお話させて頂きました。②では具体的なエピソードを交えて、さらに身近にわかりやすくお話したいと思います。
———着物のしみぬきとは———
ところで、着物の汚れ落とし、しみぬき、染色補正って、どのように行われているかご存知ですか?今や洗濯は全自動でスイッチ一つですから、着物もそんな風に洗ってるとか!? そこまでは思ってないけど、お肌のシミをとる時のように、レーザー照射でスッと消えるとか!? そんなイメージを持たれているとしたら、それは違います。
実は汚れの一つ一つ、シミの一つ一つをそれに適した洗剤や薬品を使って手作業で落としているんです。一度で取り切れない古いシミや頑固なシミは、生地の状態を見ながら根気よく進めるため、一つのシミに何十分、何時間とかかることもあります。昔と比べると、部分洗浄の設備など機械化された部分もありますが、絹などの天然デリケート素材が主流なので、一枚一枚丁寧に扱うことには変わりありません。
また、変色などを漂白や脱色の処置をした場合には、地色が一緒に消えたり、色を形成している中の1色がはがれてしまったりするので、それを元に戻す「染色補正」という高度な技術が必要になります。経年褪色などの色ムラを直す時も染色補正が必要です。
つまり何よりも重要なのは熟練した手の感覚と、見極めの出来る様々な経験値だと思います。学歴や資格や肩書きが高くどんなに知識が豊富でも、着物の扱いに慣れていても、水と油と熱と色を、既に着用済の着物の上で使いこなす事は、初めてですぐに出来る事ではありません。本やYouTubeで学んだつもりでも、同じ着物は無いし同じシミ汚れもない、一つ一つ異なる事例なのですから。ご自分でシミ取ろうとされて、擦れや輪じみが広がったり、色や柄が移ったり滲んだりして余計ひどくなった着物が最近増えてきました。小さなシミなら料金も安かったのに高くなってしまったり、直らなくなることもあるので、早めにしみぬきに出して下さいね。(関連ブログ「ご自分でされる着物のお手入れについて」)
でも、こうしてシミを抜いてまた美しく甦らせる事が出来るのは着物の大きな特徴で、「着物の」しみぬき、とわざわざ明記している所以です。製作現場をあちこち取材させて頂きましたが、どの着物も、天然繊維から糸を作り、丈夫に繊細に織り、美しく染め、細かい部分も一針一針仕立て上げる、全ての工程に職人さん達の技術が生きています。そんな日本の伝統工芸だからこそ、そして長年保ち続ける素材だからこそ、「着物のしみぬき」という私達の仕事が成り立っています。
———昔と今———
技術の世界は日進月歩、たった20年間でもいろんなことが変わりました。①でお話したように、部分的な洗浄には機械も使うようになり、精度と効率が上がり、身体的負担も減りました。昔は、桜の板の上で泥はねブラシで叩いて洗うしかなかったので、万年肩こりと腱鞘炎でした。
もちろん機械が使えない着物も多いので、桜の板と泥はねブラシは今も毎日使う必須アイテムですが、だんだん手に入りにくくなってきました。色を入れる筆もそうです。昔は、狸毛が一般的でしたが、あまり作られなくなり、今は鼬(いたち)毛の筆を使う人も増えてきました。昔は、道具が悪いと良い仕事が出来ないとばかりに、具合が悪くなればすぐ捨てて取り替える職人さんも多かったようですが、今はエコの時代でもあり、一つの道具を工夫して長く愛用する若い人も多くなりました。
薬剤も、先生から伺った話では、使い方や管理を間違えて小さな爆発、発火、時には火災が起きたりすることもあったそうです。今は作業台にはバキュームが装備されて外に排気するのが当たり前ですが、昔は使い込んだ木の作業台の工房もあったので、薬剤の気化ガスを吸い込んでしまうので身体にも悪く、発火もしやすく、また、作業台の木の灰汁が着物に付いてしまうこともあったようです。
また、薬品を使えば必ず水洗しなければなりませんが、設備投資にもお金がかかるため、水洗設備が昔の様式のまま、霧吹きやブラシで水洗作業をしている工房もありました。そのため可能なしみぬきが限られてしまい、シミの上から顔料を塗ったり、柄を描いたりして隠す施術が主流だったようです。今でも生地が弱っているなど、とれないシミの場合にはそういった手段が有効ですが、昔のその隠ぺい部分が悪目立ちしている場合など再度作業すると、隠ぺいもシミも簡単にとれる事もあるので、業界全体として技術が上がってるんだなと実感します。
広範囲の色補正には、ピースガンを使うのが一般的ですが、新人の頃に「ピースガンは自分が一番最初に導入した」と少なくともお二人の先生から聞いた(笑)くらいですから、その時代には画期的な革命だったのでしょう。今では当たり前ですが昔は広い範囲は刷毛で色補正をしていたので、今よりもっと難しかったことと思います。がその反面、洗い張りや仕立て替え、染め替えが今より多くあったので、その方法でお直しされるのも多かったようです。
昭和時代などの染色補正界は、このように肉体労働的な仕事も多く危険も伴いましたので、男性の多い業界でしたが、安全に働ける環境が整うにつれ、若い女性が増えたことも時代の変化だと思います。
しるくらんどに入社した頃、一年先輩にベテランの男性補正士の方がおられたので、その方からもいろいろ教わりました。その方は足に軽い障がいがあり、「この仕事は楽しい!それに、この仕事は、年を取っても目と手があれば出来る。」と教えて下さいました。先代から家業でも染色補正をされていて、薬品棚から新しい薬品の瓶の蓋を開ける時は必ず、「◯◯(薬品の名前)一本開けます!」と私達に声をかけておられました。女性の先輩達にはそんな慣習はなく、この仕事が危険な男性仕事だった頃を思わせるような瞬間を、その方から時折感じ取っていました。
でも、女性には女性目線だからこその細やかな気づかいのある仕事も出来ますし、着ている時のシチュエーションも動作もわかりますから、この仕事を女性がするのは自然な流れですが、その女性進出という点は、業界を支えて大きく変えた一番のポイントだと私は思います。しみぬきの仕事をしている女性はそれまでにも多くおられましたが、二十年前くらいでもまだまだ昔の風潮で、女性が前に出たり意見や行動したりすることはありませんでした。しかし意識改革がなされ、実演に出たり、ホームページからのお客様と直接お話させて頂いたり、ブログやSNSでこちらから発信するようになったことも大きな変化です。2025年9月には、大阪府枚方市でのイベントに出店し、スタッフ全員で参加したことも、少し前なら考えられなかった大きな出来事です。
こうして先代からのしるくらんどスピリッツを受け継ぎ進化させて現在も、皆様の大切なお着物を真心込めてお手入れさせて頂いてます。そんな毎日の仕事ぶりが今回少しでもお伝えできていれば幸いです。
もし、自分もやってみたいなと思われたら、いつでもお気軽にお電話・メール・ラインなどでお問い合わせ下さい。いろんな事に気がつく、子育てを終えた女性の新たなステージとしては最適だと思いますが、もちろん男女問わず大歓迎です。
また、着物の汚れやしみ、その他諸々お困りの方も、小さな事でもご遠慮なくお問い合わせ下さいね。
令和の時代に変わっても、和装や和文化を大切にされる方がいる限り、私達も着物を綺麗にするお仕事に粛々と向き合い、引き継いで参りたいと願っています。